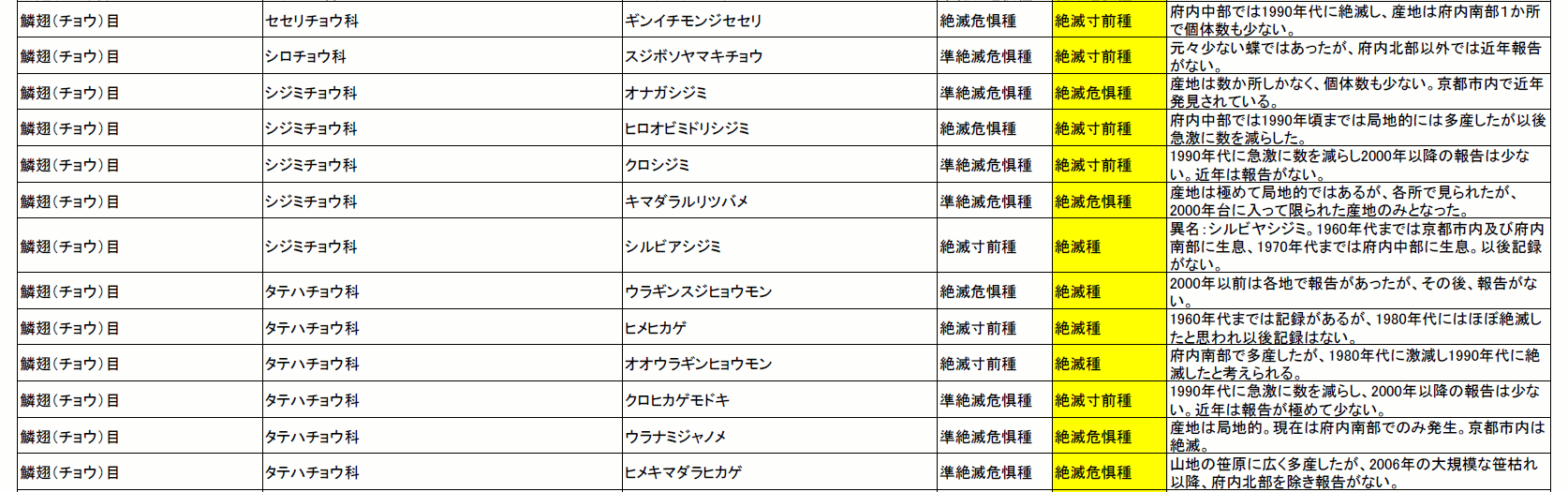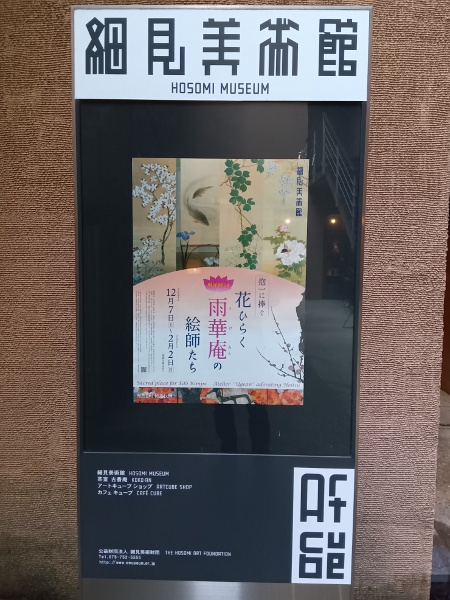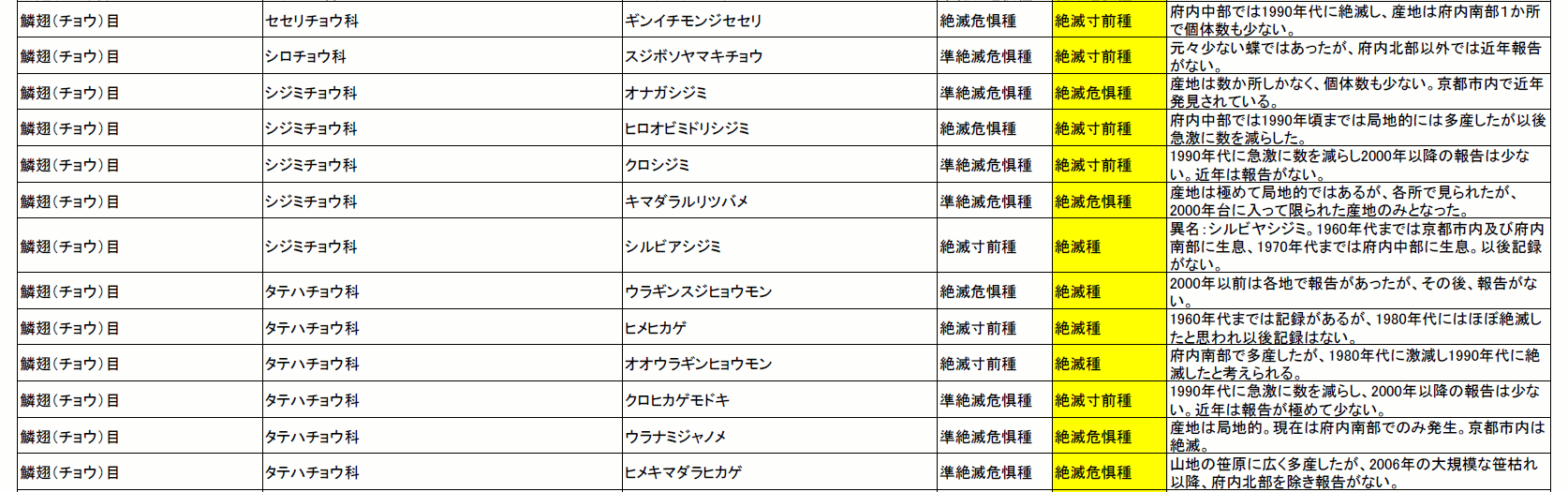・ヒメヒカゲ:『絶滅種』と断定されてますよね…。たしかに『絶滅種』としたい気持ちは、
わからんでもないのですが、京都府内、ホンマに何処にも生息してないのでし
ょうか。 本種の場合、かなり狭い湿地でも生息が可能なので、もしかすると
府内中部地域で細々と生息しているかも? というのは私の妄想でしょうか。
コメント欄には1960年代までしか記録が無いように書かれていますが、
1972年に採集された個体が確かに存在していますしねぇ…。
このカテゴリー分けをなされた方はどんな調査をされて『絶滅種』と断定した
のか、教えていただきたいものです。
・オオウラギンヒョウモン:公的機関が発行する文書内で『絶滅種』と断定するのはよろしく
ないと思っていますが、京都府内における本種は『絶滅種』と書
かれるのも仕方ないか…。
・クロヒカゲモドキ:京都府内では1990年代後半から2000年代前半にかけて西京区の小塩山山麓
から逢坂峠辺りの各所で探して完封のnull。1990年代後半から2000年代後
半にかけては府南部の綴喜郡と相楽郡の各地で探し、この辺りでは数か所で
得ることができており、特に2003年07月06日にはテニスコート程度の広さ
の谷筋にあるススキ原内で17雄1雌の他に少なくとも5頭目撃というレコー
ドが[ふしみや DB]内に記されております。いーっぱい居たんですね。
この場所の現状がどうなっているのかと Google のストリートビューで表示
してみると、こんなことになっておりました。ご覧のように発生地が根こそぎ
ぎ削り取られてしまいました。こんな状態になってはじめて、この産地では
『絶滅』と断定してもよいのだと思っています。
ところで、近年の Kさんの観察状況によると、他の京都府内の産地でも環境
は残っているのに、ほとんど見られなくなっているという結果から、上記の
表で『絶滅寸前種』とカテゴライズされていることについて、異論はござい
ません。
・ウラナミジャノメ:本種の生息地は山際と耕作地が接するような場所なので、人為による環境変
化にさらされています。なので、『絶滅危惧種』への格上げは妥当だと思い
ます。ただ、コメント欄で「京都市内は絶滅」と断言されているのは納得で
きません。山科区北部や中部では居なくなっていると思いますが、山科区南
部や伏見区が大津市と接するあたりでは生息の可能性が残っていると思って
ます。
・ヒメキマダラヒカゲ:高校生の頃、左京区の杉峠〜大見尾根でヒサマツミドリシジミを狙ってい
た頃は、びっしり生えているササ原で普通に見られていましたが、現在では
林床はツルツル、ササ原自体が存在しません。従って本種は全く見られなく
なりました。
また、一昨年と去年に山地性のゼフィルスを探しに丹後半島を訪れたとき、
きれいなササ原は広く残っているのに、見たのは本種らしき個体1頭のみで
した。なので、『絶滅危惧種』とされるのは妥当だと思います。
これまで長々と書いたのをお読みいただいた方は、「アンタは『絶滅』と断言するのがキライなんやね」と感じられたことでしょう。
そう、キライなんです。
いわゆる権威というモノを纏った組織なり個人なりが、しらみつぶしの調査(昆虫の場合そんなことできますか?)もしないで、
一旦、『絶滅』と宣言してしまうと、実は細々と生息していて後日発見された場合、
「前回、『絶滅』と断言したのは間違いでした」
と、いさぎよく発表できるのでしょうか。
そうなった場合の権威側の言い分は、
「今、採集されているアレは『放蝶由来』のモノだ」
と、証拠もなくシレッと誤魔化すんでしょうな、きっと。
もっとも、
「環境に対するテロ行為であるところの『放蝶』をしたのは私です」
と名乗り出てくれれば私も納得しますがね。

|